2021年度の日本アーカイブズ学会出版助成に採択された『続・アーカイブズ論』(明石書店、2023年)と前編『アーカイブズ論』(明石書店、2019年)について、申請者であり訳者の一人である坂口貴弘氏よりご寄稿いただきました。
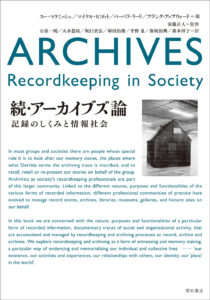
『アーカイブズ論』(明石書店、2019年) ※2018年度出版助成図書、申請者:安藤正人氏
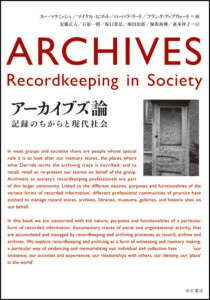
『アーカイブズ論』『続・アーカイブズ論』について
坂口貴弘
このたび、日本アーカイブズ学会の出版助成をいただき、『続・アーカイブズ論:記録のしくみと情報社会』を刊行することができた。翻訳に携わった一人として、同書を紹介するようにとのご依頼をいただいたが、そもそもこの本は、書名に「続」とあるように、2巻からなる翻訳の続編である。そして1巻目にあたる『アーカイブズ論:記録のちからと現代社会』もまた、日本アーカイブズ学会の出版助成を受けて刊行したものであった。さらにこれら2巻は、もともとオーストラリアで出版された1冊の書籍を、翻訳刊行にあたり分割した経緯もある。そこで以下では、両書をあわせて取り上げることとしたい。
概説書・教科書として読む
まず本書の特徴として、ここでは以下の2つを挙げておきたい。
第一に、英語圏を中心とした記録とアーカイブズをめぐる概念や議論を一通り網羅しており、この分野を学ぶための概説書、教科書として活用できるという点である。
例えば『アーカイブズ論』(以下「正巻」)第2章や『続・アーカイブズ論』(以下「続巻」)第5章には、古代ギリシャやローマにおけるアーカイブズの形成、フランス革命以降の近代アーカイブズ、第二次世界大戦中・戦後の全体主義体制と記録管理など、欧米中心ではあるが、世界各地のアーカイブズの歴史についての概説がある。その一方では、特に続巻の各章では、評価選別、メタデータ、編成・記述、アクセスといった実践的なテーマをめぐる最新の議論も取り上げられている。アーカイブズ学の概念と実務の両面を、その相互関係を踏まえながらトータルに把握できる書籍といえるだろう。
レコード・コンティニュアムを読み解く
第二の特徴は、本全体がレコード・コンティニュアムの概念に基づいて編集されている点である。
本書の編者の一人でもあるフランク・アップウォードが1990年代に提唱したのがレコード・コンティニュアムの理論モデルであるが、それから約10年を経て刊行された原著では、このモデルの背景にある議論が、より成熟した形で、多角的かつ具体的に概説されている。
とりわけ続巻は、「レコード・コンティニュアム」のモデルに即した構成となっている。初めの4章は「ドキュメント」〔1章〕、「レコード」〔2章〕、「アーカイブ」〔3章〕、「アーカイブズ」〔4章〕であるが、これらはレコード・コンティニュアムのモデルに登場する用語に対応したものである。その詳細については、正巻の第1章が「子供海中投げ込み事件」という具体的エピソードを例に分かりやすく説明している。また、正巻の「翻訳にあたって」でも解説しているので参照されたい。
日本でもレコード・コンティニュアムの紹介は様々になされてきたが、どうしてもこのモデルを特徴づける同心円(正巻の「翻訳にあたって」に掲載)の解釈に終始しがちである。重要なのは、このモデルは突如として登場したのではなく、記憶、証拠、組織、業務行為などと記録との関係をめぐり、アーカイブズ界で続けられてきた議論と実践がモデル化されたという点であろう。この本ではレコード・コンティニュアムにつながる諸概念を具体的な事例に基づき考察しており、このモデルを読み解く上でまたとない手がかりとなるのではないか。
『アーカイブズ論:記録のちからと現代社会』
次に、2つの巻のうち、まずは先に刊行された『アーカイブズ論』の構成を紹介したい。ここでは原著の総論にあたる第1章のほか、「機関」「専門職」「アカウンタビリティ」「法制度」「ちから(パワー)」を取り上げた章を収録している。この正巻が扱うのはいずれも、日本のアーカイブズ界をめぐる諸課題と密接に関連しているテーマばかりといえるだろう。
例えば、全国のアーカイブズ関係者が長年の課題として取り組んできたものに、アーカイブズを保存・公開する施設・機関の増加(文書館運動)と、専門職としてのアーキビスト制度の確立がある。前者の「アーカイブズ機関」〔2章〕については、既にほとんどの都道府県が公文書館にあたる機関を設置するに至った。「専門職」〔3章〕についても、日本アーカイブズ学会による登録アーキビストや、国立公文書館による認証アーキビストという形で実績を重ねつつある。
この本の原著が刊行されたのは2005年だが、翻訳の完成は18年後となってしまった。この間は、日本のアーカイブズ界にとって大きな変化の時期であったといってよい。とりわけ公文書管理法の成立(2009年)は、「アカウンタビリティ」〔4章〕を果たす道具としての公文書とその管理の重要性を広く社会に認識せしめる契機となった。その結果、政府においては公文書監察室の設置など、公文書の管理に対する「法的ガバナンス」〔5章〕の強化をもたらした。一方で、何が公文書として記録され、何が保存されるかは、単なる機械的作業ではなく「社会的ちから」〔6章〕の反映でもあることを、人々は意識するようになりつつある。このような日本のアーカイブズ界の経験と照らし合わせながら『アーカイブズ論』を繙くと、より深い示唆が得られるように思う。
『続・アーカイブズ論:記録のしくみと情報社会』
最新刊である続巻については、各章の内容をかいつまんで紹介したい。
「私たちはドキュメントの網の目(ウェブ)の中に生きている」という一文から始まるのが第1章である。ドキュメントの例として一般的に想定されがちな文書の形だけでなく、パフォーマンス・アートや樹木の年輪なども挙げられる。これら様々なドキュメントの分析には“型”(構造)への理解が必要であることが、映画や写真の例を通して示している。電子ネットワーク環境ではドキュメントとプロセスの関係が変容しゆくことについても言及がある。
このドキュメントが何らかのシステムに取り込まれると、レコードと位置づけられるようになる。第2章はスーパーのレシート、大臣への陳情書、学生の成績記録など具体例を挙げながら、レコードとその管理システムが果たすべき役割について論じる。欧州の伝統的な「登録システム」や記録管理の国際標準についても解説されており、これらの実際と背景を知る上で役に立つ。
組織や個人、家のレコードの総体は、ここではアーカイブと称される。第3章は組織の構造とアーカイブの関係について述べており、分散型組織や仮想型組織などの新たな形態についても考察される。その上で、アボリジニのように口承の形で物語が伝承される集団にとってのアーカイブとは、という問題にも論を進めている。
様々な組織や個人のアーカイブの集合体が、第4章で取り上げられる複数形のアーカイブズにあたる。多様なアーカイブズを扱う上で編み出されたフォンド尊重の原則と、オーストラリアにおけるシリーズ・システムの関係を説明している。マクロ評価選別やトータル・アーカイブズ、電子記録の保存、アクセスとメタデータなどの実践的課題についても多くのページが割かれている。
本書全体の理論的枠組みを提供する役割を果たすのが、第5章「レコード・コンティニュアム」である。このモデルの基礎となった社会学者アンソニー・ギデンズの構造化理論に始まり、ベルクソンやフーコー、リオタールやデリダといった現代思想の成果を縦横に参照しつつ議論が展開されている。「記録のしくみと情報社会」について語るには、目先の現象への対処だけでなく、このような幅広い考究と厚みのある思索が本来欠かせないことを教えてくれる。
アーカイブズと密接不可分な関係にある「記憶」の問題を論じるのが、最後の第6章である。口承伝承や回想録と文書との関係、スターリンやナチスの政権下における記録の破棄、旧ユーゴスラビア紛争における文化遺産の破壊など、多様な事例を挙げながら人々の記憶とアーカイブズの相互作用について分析している。
おわりに
この本は翻訳書であること、また従来のアーカイブズ関連書籍では見慣れない用語も頻出することから、ややとっつきにくい面があるかもしれない。そのような読者におすすめしたいのが、各巻の末尾に付されている「事項索引」から読む方法である。ここでは本書の内容に関連するキーワードが、掲載ページの順序と関係なく五十音順に並んでいる。事項索引を一覧すると、目次や章のタイトルからは想像できないような興味深いテーマが多数取り上げられていることに気づく。
幸いなことに原著の編者も「本書について」の中で、この本は「どのような順番で読んでも差し支えない」〔正巻30頁〕と言ってくれている。自身が詳しく知りたいトピックを、章の壁を越えて自在に“横断検索”しながら読むのも一興ではないだろうか。
《監修者・訳者プロフィール》
・安藤正人
国文学研究資料館名誉教授、元学習院大学大学院人文科学研究科アーカイブズ学専攻教授
・石原一則
元神奈川県立公文書館資料課長、元日本アーカイブズ学会会長。2016年没
・大木悠佑
独立行政法人国立公文書館統括公文書専門官室公文書専門官
・坂口貴弘
創価大学創価教育研究所講師
・塚田治郎
日本アーカイブズ学会会員。2020年没
・平野泉
立教大学共生社会研究センターアーキビスト
・保坂裕興
学習院大学文学部教授(大学院アーカイブズ学専攻担当)。日本アーカイブズ学会会長
・森本祥子
東京大学文書館准教授
《申請者》
・坂口貴弘
創価大学創価教育研究所講師

